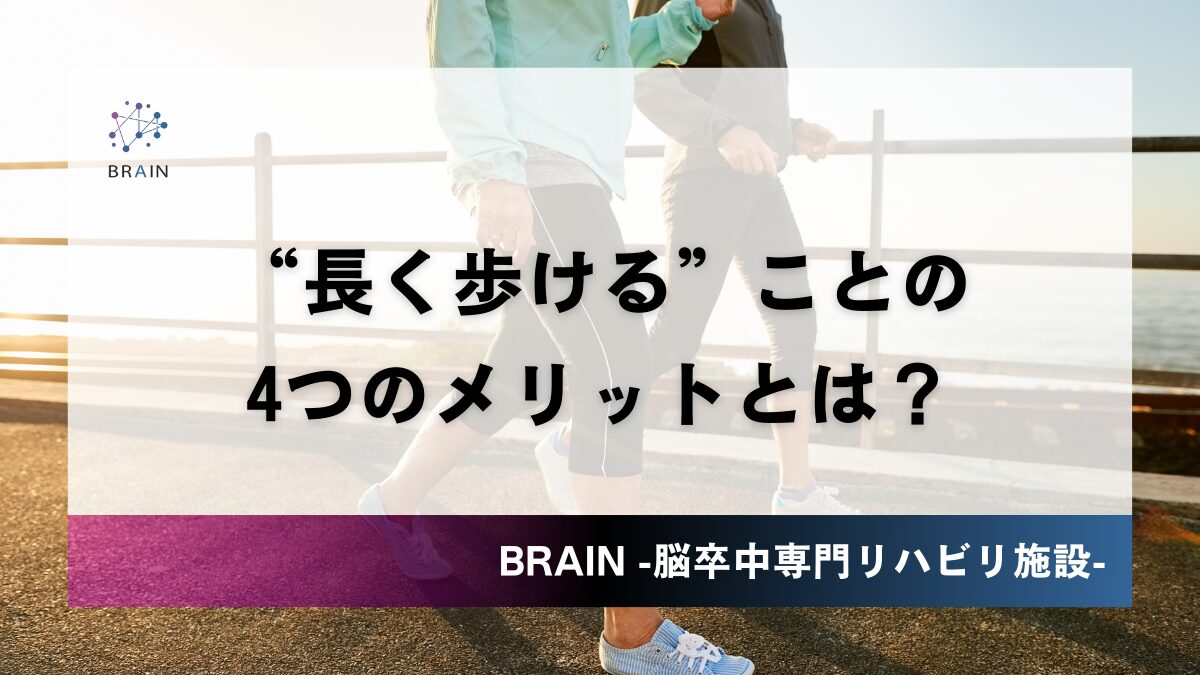
脳卒中を発症すると “歩行障害(ほこうしょうがい)” が表れます。
歩行障害は、主に以下の4つに分けられます。
- 歩行自立度の低下(ひとりで歩けない)
- 歩行スピードの低下(歩くスピードが遅くなる)
- 歩行距離の短縮(連続で歩ける距離が短くなる)
- 歩容の乱れ(歩きかたの乱れ)
本記事では “歩行距離の短縮” つまり、 ”連続して長く歩くことが難しい状態”に注目します。
リハビリによって長く歩けるようになったときに得られるメリットを、研究結果も交えてご紹介します。
情報の信頼性について
・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。
・本記事の情報は、信頼性の高いシステマティックレビュー研究から得られたデータや、学術雑誌に投稿されたLetter to Editorを引用しています。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー
エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!
詳細はこちら
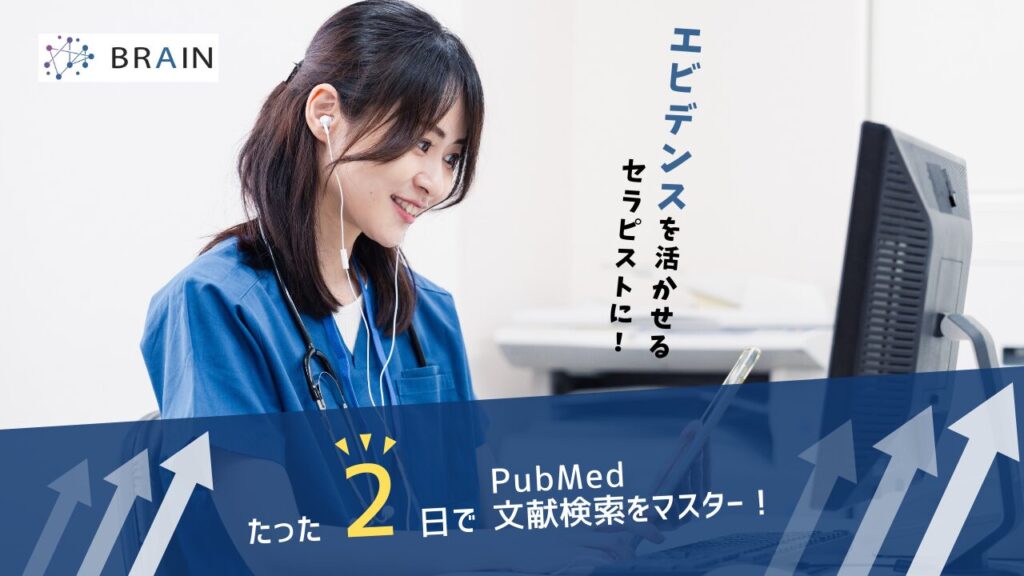
文献検索CAMP
PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。
詳細はこちら
脳卒中患者さんが “長く歩ける” ことの4つのメリット
脳卒中患者さんが “長く歩ける” ことの4つのメリットは次のとおりです。
- 外出しやすくなり、活動の幅が広がる
- 転びにくく、安全に歩ける
- 生活の中でできることが多い(参加の向上)
- 健康に直結する生活の質(QOL)が高まる
詳しく解説します。
“長く歩ける” とは?
まず、“長く歩ける”とはどういうことかを説明します。
ここでいう“長く歩ける”とは、「休まずに歩ける距離が長い」という意味です。
脳卒中を発症すると、多くの場合、長く歩くことが難しくなります。
これを専門的には「歩行距離の短縮」と呼びます。その背景には、筋力や心肺機能の低下、脳卒中による運動麻痺などが関係しています。
歩行距離が短くなると、次のようなことが起きやすくなります。
- 少し歩いただけで疲れてしまう
- 途中で休憩しないと目的地まで行けない
- 買い物や外出が面倒になり、家にこもりがちになる
つまり、歩行距離が短くなることは、日常生活や社会参加の機会を減らしてしまうサインともいえます。
まとめると、
- 脳卒中によって運動麻痺や体力低下が起こる
- その結果、連続して長く歩くことが難しくなる(歩行距離の短縮)
- 生活や社会参加の場面が減ってしまう
という流れです。
しかし、歩行距離の短縮はリハビリで改善が可能です。
次に、リハビリを通して“長く歩ける”ようになったときに得られる4つのメリットをご紹介します。
メリット① 外出しやすくなり、活動の幅が広がる

“長く歩ける” 人は、外出しやすくなり、活動の幅が広がる傾向があります。
2020年の研究では、脳卒中患者さん83人を対象にし、退院時の「連続歩行距離」と、退院6ヶ月後の「外出回数」の関係を調べました。
その結果、退院時に長く歩ける人ほど、半年後の外出回数が多いことがわかりました。
また、他の2020年の研究でも同様の結果を報告しています。
この研究では、退院時に長く歩ける人は、退院後1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月のいずれにおいても、歩行活動の量(1日の歩数)、頻度(連続歩行時間)、強度(負荷の高い歩行が可能か)いずれも高い傾向が確認されました。
歩行活動の量・頻度・強度は、将来の健康維持に関わる重要な指標です。
つまり、退院時点で長く歩けることは、その後も健康的に過ごせる可能性を高める要因の一つといえます。
メリット② 転びにくく、安全に歩ける

“長く歩ける” 人は、転びにくい傾向があります。
2014年の研究では、脳卒中患者さん64人を対象に、病院を退院するときの「短距離」と「長距離」の歩行スピードの差と、退院後1年間の転倒との関係を調べました。
結果として、短距離でも長距離でも同じ速度で歩ける人ほど、退院後の転倒が少ないことがわかりました。
一方、短距離では速く歩けても、長距離になると速度が落ちる人は、1年間で1〜2回の転倒を経験していました。
長距離を一定のスピードで歩くには、心肺機能や持久力が欠かせません。
これらを鍛えることが、転倒予防や将来の怪我のリスク低減につながる可能性があります。
メリット③ 生活の中でできることが多い(参加の向上)

“長く歩ける” 人は、日常生活でできる活動が多い傾向があります。
専門的には、これを「社会参加の幅が広い」と表現します。
2021年の研究では、脳卒中患者さん52人を対象にし、「長く歩けること」と「日常生活での活動範囲」の関係を調べました。
結果として、リハビリを通じて歩行距離が伸びるほど、生活の中でこなせる活動も増える傾向があることがわかりました。
つまり、長く歩けるようになるにつれて、生活の中でできることも多くなっていく傾向があるということです。
もちろん、社会参加の広がりは歩行距離だけで決まるわけではありません。
例えば、会話能力などのコミュニケーション面や、自宅周囲のバリアフリー化といった環境も大きく影響します。
したがって「長く歩ければ必ず社会参加が広がる」と断言はできませんが、歩行距離の向上は社会参加を後押しする重要な要因の一つといえます。
メリット④ 健康に直結する生活の質(QOL)が高まる

“長く歩ける” 人は、身体の調子や日常生活の満足度が高い傾向があります。
2025年の研究では、脳卒中患者さん106人を対象にし、身体の健康や生活のしやすさ(QOL)と、6分間で歩ける距離との関係を調べました。
その結果、“長く歩ける”人ほど、身体の動きや日常生活のしやすさ(QOL)の評価が高いこともわかりました。
つまり、 “長く歩ける” ということは、買い物や外出、友人との交流など、日常生活をより楽しむ力につながる可能性が高いということです。
まとめ
本記事で紹介した4つのメリットをまとめます。
- 外出しやすくなり、活動の幅が広がる
- 転びにくく、安全に歩ける
- 生活の中でできることが多い(参加の向上)
- 健康に直結する生活の質(QOL)が高まる
全体的に、“長く歩ける”人は、長期的に見たときに健康でいられる可能性が高いといえます。
リハビリによって “長く歩ける” ようになります。
歩行距離を伸ばすリハビリについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
ただし、歩行スピードを上げるリハビリと比べると、歩行距離を伸ばすためのリハビリは難しい傾向にあります。
よかったら、担当の理学療法士さんと相談しながら、ご自身が現状どれくらい長く歩けるのか、長く歩けるようになるためにはどのようなリハビリをすべきか、検討されてみてはいかがでしょうか。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!
参考文献
Karageorge A DCP, Vargas J BPhty, Ada L PhD, Kelly PJ PhD, McCluskey A PhD. Previous experience and walking capacity predict community outings after stroke: An observational study. Physiother Theory Pract. 2020 Jan;36(1):170-175. doi: 10.1080/09593985.2018.1484829. Epub 2018 Jun 14. PMID: 29902102.
Mahendran N, Kuys SS, Brauer SG. Which impairments, activity limitations and personal factors at hospital discharge predict walking activity across the first 6 months poststroke? Disabil Rehabil. 2020 Mar;42(6):763-769. doi: 10.1080/09638288.2018.1508513. Epub 2019 Feb 6. PMID: 30724628.
Morone G, Iosa M, Pratesi L, Paolucci S. Can overestimation of walking ability increase the risk of falls in people in the subacute stage after stroke on their return home? Gait Posture. 2014 Mar;39(3):965-70. doi: 10.1016/j.gaitpost.2013.12.022. Epub 2013 Dec 25. PMID: 24440427.
de Rooij IJM, Riemens MMR, Punt M, Meijer JG, Visser-Meily JMA, van de Port IGL. To What Extent is Walking Ability Associated with Participation in People after Stroke? J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021 Nov;30(11):106081. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.106081. Epub 2021 Sep 7. PMID: 34507257.
Marklund I, Fure B, Klässbo M, Liv P, Stålnacke BM, Hu X. Post-stroke health-related quality of life following lower-extremity constraint-induced movement therapy – An observational survey study. PLoS One. 2025 May 8;20(5):e0323290. doi: 10.1371/journal.pone.0323290. PMID: 40341838; PMCID: PMC12061391.











