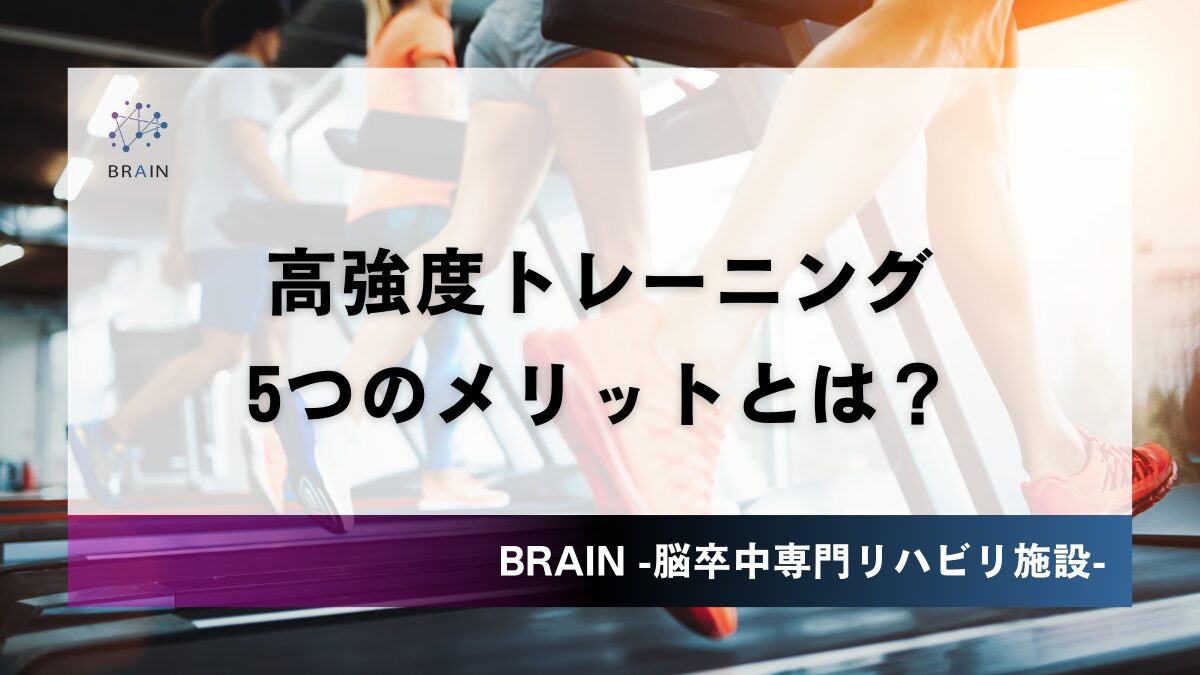
脳卒中のあと、リハビリを続けていても「この先、どこまで回復できるんだろう…」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。
特に、「体力が落ちて長く歩けない」「頭が働きにくくなった気がする」といった悩みは、ご本人もご家族も大きな負担になります。
実は近年の研究で、少しきつい運動=高強度トレーニングが、心肺機能や歩行スピード、さらには認知機能まで改善させる可能性があることが分かってきました。
昔は、「筋緊張が強くなったり、心臓や血管に負担がかかるから、脳卒中患者さんにキツい運動はよくない」と考えられていたため、セラピストから「楽な運動でいいですよ」と助言されていた方もいるかもしれません。
しかし、最新の研究ではその考えが見直されつつあり、むしろ少しきつい運動の方が大きな効果をもたらすことが分かってきました。
今回は、その科学的根拠と具体的なメリットを、分かりやすくご紹介します。
情報の信頼性について
・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。
・本記事の情報は、信頼性の高い観察研究から得られたデータを引用しています。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー
エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!
詳細はこちら
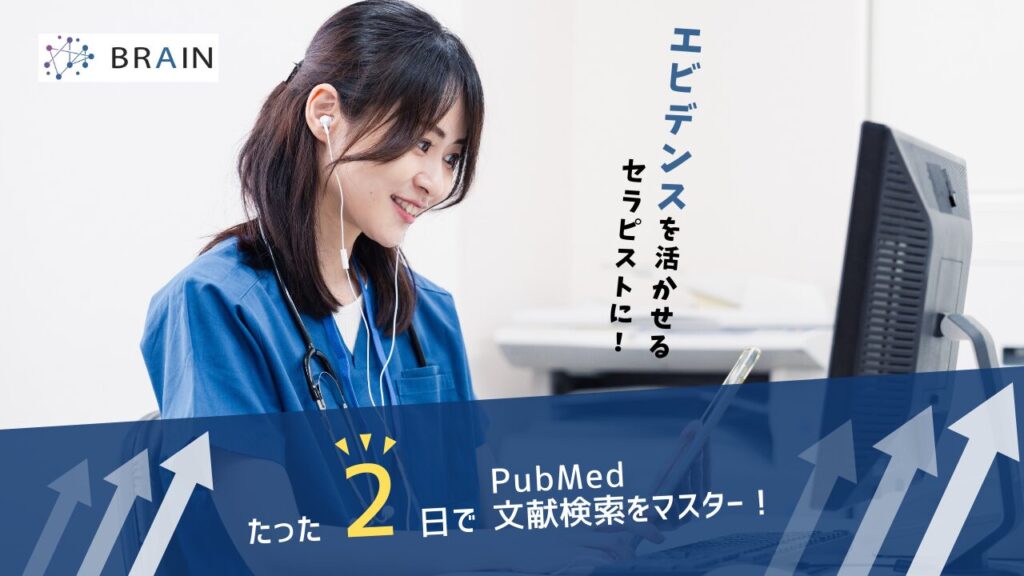
文献検索CAMP
PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。
詳細はこちら
脳卒中患者さんが高強度トレーニングをする5つのメリット
5つのメリットは以下の通りです。
- 心肺機能が向上する
- 歩行スピードが速くなる
- 長く歩けるようになる
- 高次脳機能がよくなる
- 脳由来神経栄養因子が増える
以下、詳しく解説します。
高強度トレーニングとは?

高強度トレーニングは、少し息が切れるくらいしっかり体を動かす練習で、歩く力や体力を伸ばすために有効なリハビリ方法です。
特に、速く歩く練習や心臓や肺にしっかり負荷をかける有酸素運動(息が少し上がる運動)を指します。
リハビリ現場では、心拍数(脈の速さ)を目安にして運動の強さを決めています。
「高強度」とは、普段よりかなり速い脈拍になるくらいの運動のことです。
年齢によって異なるのですが、
- 40歳の方は最大心拍数が約180回/分 → 高強度はおよそ125〜160回/分
- 60歳の方は最大心拍数 約160回/分 → 高強度はおよそ110〜145回/分
- 70歳の方は最大心拍数が約150回/分 → 高強度はおよそ105〜135回/分
となります。つまり、同じ「高強度」でも、40歳の方にとっては「心拍数125〜160回/分」ですが、70歳の方にとっては「心拍数105〜135回/分」になるのです。そのため、年齢や体の状態に合わせて調節することが大切です。
実際には、トレッドミルマシン(ベルトコンベアのような機械)で、速いペースで歩く練習が多く取り入れられます。
従来、「脳卒中患者さんにとって強度の高い運動は危険だ」と考えられてきましたが、しっかりとデータをとってみると強度が高いからといって危険度が上がるわけではない」ことが明らかになり、近年では主要なリハビリの選択肢のひとつになってきています。
メリット① 心肺機能が向上する
2017年の研究では、システマティックレビューの手法を用いて、世界中の論文を集め、脳卒中患者さんに対する高強度トレーニングの有効性を調査しました。
598人分のデータを解析した結果、運動の強度が高いほど心肺機能の改善効果が大きいことが明らかになりました。
心肺機能とは?
「心臓や肺がどれだけ効率よく酸素を全身に送り、筋肉がその酸素をどれだけ使えるか」という能力のことです。
さらに、中強度(64~76%HRmax)の有酸素運動と、高強度(77~93%HRmax)の有酸素運動を比較したところ、改善効果は2倍以上の差があることが示されました。
このことから、高強度トレーニングは脳卒中患者さんの心肺機能を大きく向上させる可能性があるといえます。
メリット② 歩行スピードが速くなる
歩行スピードが速いことには、次の5つのメリットがあります。
- 脳卒中発症(再発)のリスクが低い
- 歩きかたがよい
- 日常生活動作(ADL)の自立度が高い
- 生活の質(QOL)が高い
- 社会参加レベルが高い
2019年の研究では、345人のデータを分析した結果、低〜中強度のトレーニングと比べて、高強度トレーニングの方が歩行スピードの改善度が大きいと報告されています。
歩行スピードはリハビリによって改善可能ですが、低〜中強度よりも高強度の有酸素運動の方が効果的だということです。
また、2021年の研究では、心肺機能の低下が歩行スピードを遅くする一因であることも示されています。
したがって、
高強度トレーニングを行う → 心肺機能が向上する → 歩行スピードが速くなる
という好循環が期待できると考えられます。
メリット③ 長く歩けるようになる
長く歩けるようになることには、次の4つのメリットがあります。
- 外出しやすくなり、活動の幅が広がる
- 転びにくく、安全に歩ける
- 生活の中でできることが増える(参加の向上)
- 健康に直結する生活の質(QOL)が高まる
2017年の研究では、734人のデータを分析した結果、高強度トレーニングは中強度トレーニングと比べて歩行距離の改善効果が高いことが報告されました。
歩行距離はリハビリで改善可能ですが、歩行スピードを上げるよりも難易度が高いことが知られています。
別の2017年の研究では、脳卒中患者さんに対してトレッドミルトレーニングの有効性を検証しました。
トレッドミルトレーニングとは?
「トレッドミルトレーニング」とは、ベルトコンベアのように床が自動で動く機械(トレッドミル)を使った歩行練習のことです。ジムのランニングマシンとしても一般的ですが、リハビリにおいても重要な役割を果たします。
この研究では、歩行スピードを改善するには「週3回以上」のリハビリが有効であるのに対し、歩行距離を延ばすには「週5回以上」のリハビリが必要であることが示されました。
これはあくまでも一例ですが、このように、歩行スピードは比較的改善しやすい一方、歩行距離を延ばすには工夫が求められます。
その工夫の一つが高強度トレーニングです。低〜中強度の有酸素運動よりも高強度の方が歩行距離を伸ばしやすいと報告されており、歩行距離の改善を目指す上で高強度トレーニングは妥当な方法といえるでしょう。
メリット④ 認知機能がよくなる

脳卒中を発症すると、手足のまひや言葉の障害に加えて、「考える力」や「覚える力」といった認知機能が低下することがあります。これを「脳卒中後認知機能低下」と呼びます。
認知機能とは、
- 記憶する力(ものを覚える・思い出す)
- 注意する力(集中する、気をそらさない)
- 判断する力(状況を理解して選択する)
- 言葉を使う力(話す・理解する)
- 計画する力(順序立てて行動する)
など、日常生活を送るうえで欠かせない“頭の働き”のことです。
脳卒中で脳の一部にダメージが生じると、これらの働きが弱くなる場合があります。たとえば、
- 話している内容をすぐに忘れてしまう
- 複数のことを同時にこなせない
- 慣れた道でも迷いやすい
- 段取りを組んで行動するのが難しい
といった症状が見られることがあります。
2021年の研究では、脳卒中後の認知機能低下が日常生活の自立度や社会参加に影響を及ぼすことが報告されています。
認知機能の低下は、患者さんご本人だけでなくご家族にとっても大きな負担になりますが、リハビリや環境調整によって改善や補うことが可能です。
高強度トレーニングも、その改善に有効であることが報告されています。
2024年の研究では、脳卒中患者さんにおいて、中〜高強度トレーニングが低強度トレーニングよりも認知機能の改善に有効であることが示されました。
つまり、「楽にできる運動」ではなく「少しキツい運動」を取り入れることで、認知機能の向上が期待できるということです。
メリット⑤ 脳由来神経栄養因子が増える
高強度トレーニングをすることで、脳由来神経栄養因子(Brain-Derived Neurotrophic Factor:BDNF)が増えることが報告されています。
脳由来神経栄養因子とは、脳の成長や回復を助ける栄養のようなものです。
BDNFは脳の中で作られ、
- 神経細胞を元気に保つ
- 傷ついた神経を修復する
- 新しい神経のつながり(シナプス)を強くする
といった働きをしています。つまり、脳の学習や記憶、回復に欠かせないサポーターといえます。
脳卒中のあとには神経がダメージを受けていますが、BDNFがしっかり働くことで、身体の動きや記憶の回復が進みやすいことが研究で示されています。
2024年の研究では、脳卒中患者さんが中〜高強度トレーニングを行った場合、低強度トレーニングよりもBDNFが多く増えることが明らかになりました。
ここまで歩行スピードや歩行距離、認知機能に対して高強度トレーニングが有効であることをお伝えしてきましたが、その背景にはBDNFの増加が関わっているのかもしれません。
高強度トレーニングは危険ではない
これまで「脳卒中の方に高強度トレーニングを行うと、心臓や血管に負担が大きく危険だ」と考えられてきました。
しかし、最新の研究ではそのような心配は必ずしも当てはまりません。
複数の研究で高強度トレーニングの安全性が調べられていますが、いずれも「中強度や低強度の運動と比べて、転倒や痛み、皮膚の損傷といった怪我のリスクが特別に高いとは言えない」と結論づけています(Luo L 2019; Luo L 2020; Boyne P 2024)。
さらに、2024年の報告では、高強度トレーニングによる重い副作用(重篤な有害事象)の発生率は398人中1人未満と推定され、リスクは極めて低いとされています。
もちろん、どのような運動でも怪我の可能性がゼロになることはありません。そのため、必ず専門家と相談しながら、体調や安全に配慮して取り組むことが大切です。
まとめ
脳卒中患者さんが高強度トレーニングをする5つのメリットは以下の通りです。
- 心肺機能が向上する
- 歩行スピードが速くなる
- 長く歩けるようになる
- 高次脳機能がよくなる
- 脳由来神経栄養因子が増える
脳卒中のあと、「もうこれ以上は良くならないのでは」と感じてしまうこともあるかもしれません。
ですが、研究の積み重ねによって、少しきつい運動=高強度トレーニングが、心肺機能や歩行能力、さらには認知機能や脳そのものの回復に役立つことが分かってきました。
もちろん、取り組む際には主治医やリハビリの専門家と相談し、無理のない範囲で安全に行うことが大前提です。
小さな積み重ねが、回復につながる可能性があります。そのことを知っているだけでも、前に進む力になると思います。
どうか、希望を持って、工夫しながらリハビリに取り組んでみてください。
参考文献
Boyne P, Welge J, Kissela B, Dunning K. Factors Influencing the Efficacy of Aerobic Exercise for Improving Fitness and Walking Capacity After Stroke: A Meta-Analysis With Meta-Regression. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Mar;98(3):581-595. doi: 10.1016/j.apmr.2016.08.484. Epub 2016 Oct 12. PMID: 27744025; PMCID: PMC5868957.
Li Z, Guo H, Yuan Y, Liu X. The effect of moderate and vigorous aerobic exercise training on the cognitive and walking ability among stroke patients during different periods: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2024 Feb 23;19(2):e0298339. doi: 10.1371/journal.pone.0298339. PMID: 38394189; PMCID: PMC10889575.
Boyne P, Miller A, Kubalak O, Mink C, Reisman DS, Fulk G. Moderate to Vigorous Intensity Locomotor Training After Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis of Mean Effects and Response Variability. J Neurol Phys Ther. 2024 Jan 1;48(1):15-26. doi: 10.1097/NPT.0000000000000456. Epub 2023 Sep 7. PMID: 37678805; PMCID: PMC10843766.
Luo L, Zhu S, Shi L, Wang P, Li M, Yuan S. High Intensity Exercise for Walking Competency in Individuals with Stroke: A Systematic Review and MetaAnalysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Dec;28(12):104414. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104414. Epub 2019 Sep 27. PMID: 31570262.
Blokland I, Gravesteijn A, Busse M, Groot F, van Bennekom C, van Dieen J, de Koning J, Houdijk H. The relationship between relative aerobic load, energy cost, and speed of walking in individuals post-stroke. Gait Posture. 2021 Sep;89:193-199. doi: 10.1016/j.gaitpost.2021.07.012. Epub 2021 Jul 21. PMID: 34332288.
Mehrholz J, Thomas S, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 17;8(8):CD002840. doi: 10.1002/14651858.CD002840.pub4. PMID: 28815562; PMCID: PMC6483714.
Stolwyk RJ, Mihaljcic T, Wong DK, Chapman JE, Rogers JM. Poststroke Cognitive Impairment Negatively Impacts Activity and Participation Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Stroke. 2021 Jan;52(2):748-760. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.032215. Epub 2021 Jan 25. PMID: 33493048.
Luo L, Meng H, Wang Z, Zhu S, Yuan S, Wang Y, Wang Q. Effect of highintensity exercise on cardiorespiratory fitness in stroke survivors: A systematic review and meta-analysis. Ann Phys Rehabil Med. 2020 Jan;63(1):59-68. doi: 10.1016/j.rehab.2019.07.006. Epub 2019 Aug 26. PMID: 31465865.











