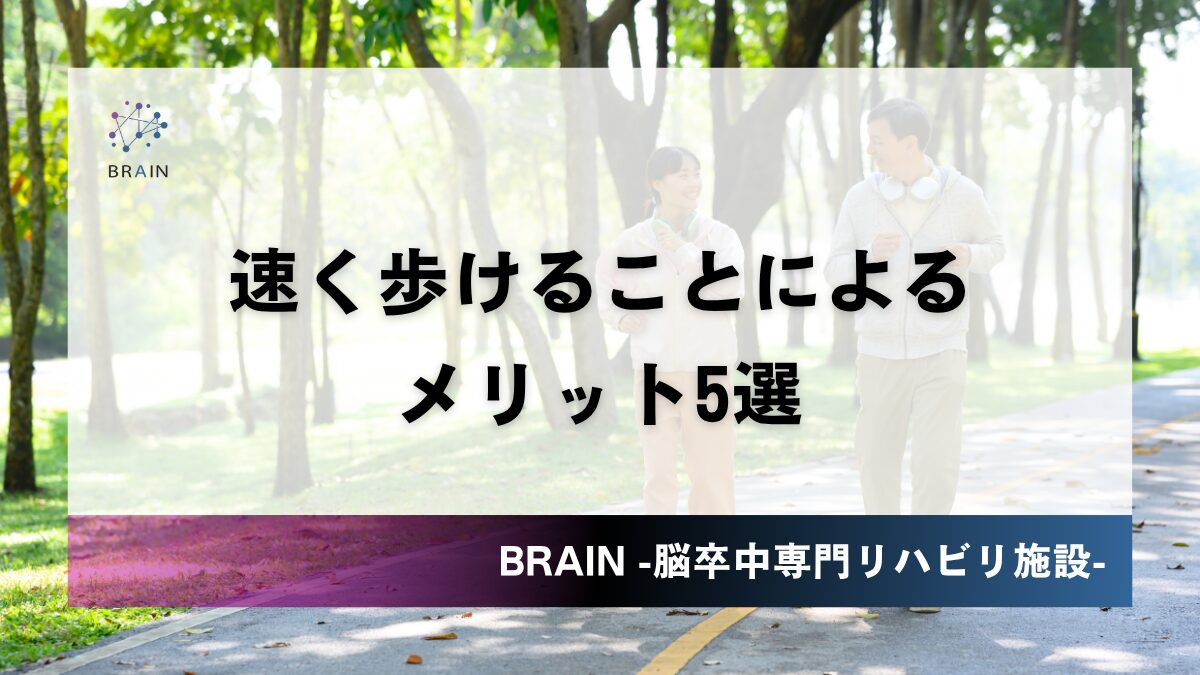
脳卒中を発症すると歩行障害(ほこうしょうがい)が表れます。
歩行障害は、主に以下の4つに分けられます。
- 歩行自立度の低下(ひとりで歩けない)
- 歩行スピードの低下(歩くスピードが遅くなる)
- 歩行距離の短縮(連続で歩ける距離が短くなる)
- 歩容の乱れ(歩きかたの乱れ)
脳卒中を発症した直後の急性期や回復期では、「歩行自立」を目的としたリハビリが行われることが多いです。
「歩行スピード」を意識したことがない方も多いかもしれません。
しかし、歩きをさらによくしたいのであれば、歩行スピードを上げることはとても大事です。
本記事では、脳卒中患者さんにおける歩行スピードが速いことの5つのメリットについて解説します。
情報の信頼性について
・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。
・本記事の情報は、信頼性の高いシステマティックレビュー研究から得られたデータや、学術雑誌に投稿されたLetter to Editorを引用しています。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー
エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!
詳細はこちら
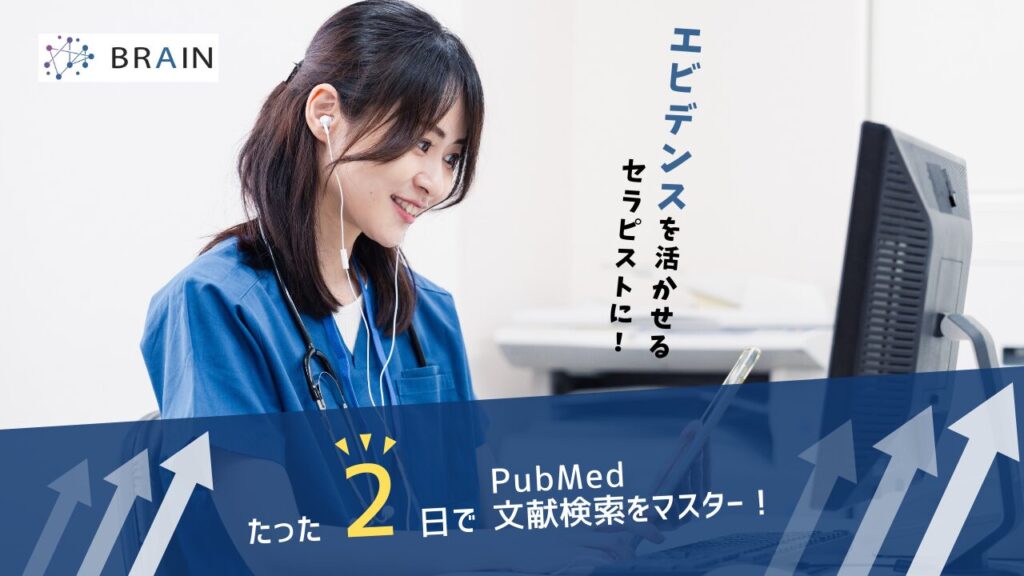
文献検索CAMP
PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。
詳細はこちら
脳卒中後の歩行スピードが速いことの5つのメリット
歩行スピードが速いことのメリットは次の5つです。
- 脳卒中発症(再発)のリスクが低い
- 歩きかたがよい
- 日常生活動作(ADL)の自立度が高い
- 生活の質(QOL)が高い
- 社会参加レベルが高い
以下、詳しく解説します。
メリット① 脳卒中発症(再発)のリスクが低い

歩行スピードが速い人は、脳卒中発症のリスクが低いことが明らかになっています。
2020年の研究では、135,645人の高齢者を対象にし、歩行スピードと脳卒中発症リスクの関係を調査しました。
結果として、歩行スピードが速い人たちは、遅い人たちと比べ、脳卒中発症のリスクが44%低くなることが明らかになりました。
また、歩行スピードが1km/h早くなるごとに、脳卒中発症リスクが13%減少することも報告されました。
また、2017年の研究では、1,486人の高齢者を対象にし、歩行スピードと脳卒中発症リスクの関係を6年間にわたって調査しました。
結果として、
- ①歩行スピードが遅い人の脳卒中発症率は13.3%
- ②歩行スピードが中くらいの人の脳卒中発症率は9.4%
- ③歩行スピードが速い人の脳卒中発症率は5.0%
であったことが明らかになりました。
歩行スピードが速くても脳卒中発症のリスクをゼロにできるわけではありませんが、遅い人たちと比べるとそのリスクは低いようです。
また、2024年の研究では、発症7日以内の脳卒中またはTIA患者さん1,542人を対象に、病院を退院するときおよび発症から3ヶ月時点での歩行スピードと、1年後の状況について調査をしました。
TIA(Transient Ischemic Attack:一過性脳虚血発作)とは?
TIAとは、数分〜数時間で自然に回復する一時的な脳の血流障害です。
結果として、病院を退院するときおよび発症から3ヶ月時点での歩行スピードが速いほど、1年後の機能回復不良、認知機能障害、脳卒中再発、および複合血管イベントのリスクが低いことが示されました。
複合血管イベントとは?
複合血管イベントとは、脳卒中や心筋梗塞など、複数の血管疾患の発症をまとめて示す指標です。
このことから、脳卒中を発症した患者さんにおいても、歩行スピードが速いほうが、脳卒中再発のリスクが低いと言えます。
これらのデータから、『歩行スピードが速いほうが、脳卒中発症(再発)リスクが低い』と言えるでしょう。
メリット② 歩きかたがよい

歩行スピードが速い人は、歩容(歩きかた)がよいことが明らかになっています。
2025年の研究では、脳卒中患者さん22人を対象にし、歩行スピードと歩きかたとの関係を調査しました。
結果として、歩行スピードが遅い脳卒中患者さんのグループは、健常者や歩行スピードが速い脳卒中患者さんのグループと比較して、
- 骨盤の前後方向への動きが大きくなってしまう
- 股関節の内転・外転(左右の動き)が小さくなってしまう
- 股関節伸展角度(脚を身体の後ろに伸ばすときの角度)が小さくなってしまう
- 股関節屈曲(脚を持ち上げる動き)の力が弱くなってしまう
ことが明らかになりました。
簡単に言うと、『歩行スピードが遅い脳卒中患者さんは、歩きかたが乱れている』ということです。
なお、歩行スピードと歩容(歩きかた)は、お互いに影響し合っていると考えられます。
まず、『歩行スピードが遅いから歩きかたが乱れる』という側面があります。
これは2019年の研究で実証されており、健常者も歩行スピードを下げると歩きかたが乱れることが報告されています。
一方で、『歩きかたが乱れているから歩行スピードが遅い』という側面もあります。
運動麻痺の影響で歩幅が小さくなってしまったり、脚の回転数が下がってしまう(=歩きかたの乱れ)と、歩行スピードが低下します。
したがって、一概に『歩行スピードが遅いから歩きかたが乱れる』とは言えません。
ただし、『歩行スピードが遅い人は歩きかたが乱れている傾向がある』というデータは一貫して報告されており、関係はあると考えてよいでしょう。
メリット③ 日常生活動作(ADL)の自立度が高い
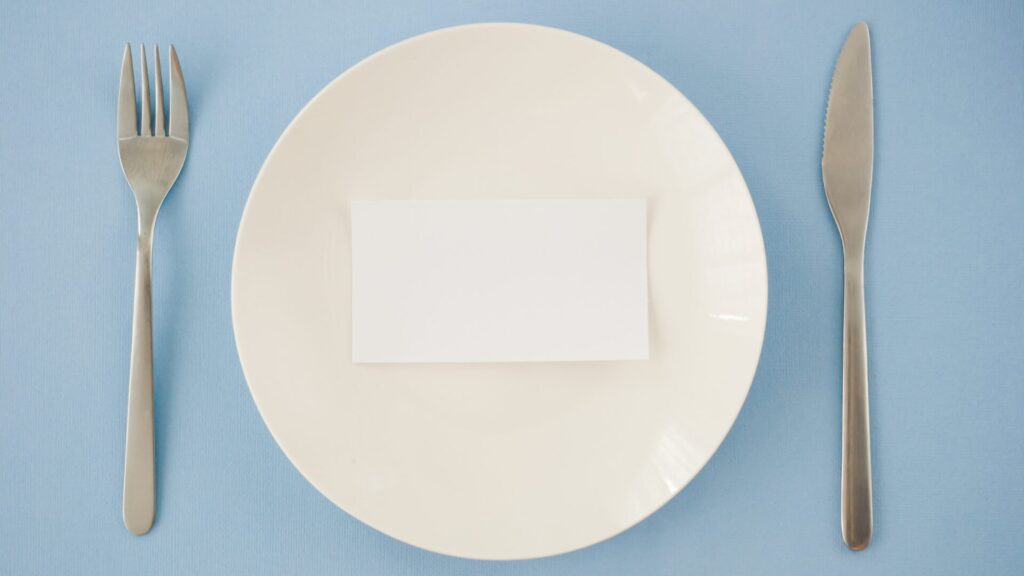
歩行スピードが速い人は、ADLの自立度が高いことが明らかになっています。
ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)とは?
ADLとは、食事・着替え・排泄・入浴・移動など、日常生活を送るうえで基本となる動作のことです。
歩行自立度が高い/移動できる範囲が広い
ADLの中に「移動」があります。
歩行スピードが速い人ほど、移動できる範囲が広がったり、ひとりで歩けるようになる傾向があります。
2015年の研究では、脳卒中患者さん103人を対象にし、『地域での制限のない移動が可能』と判断される基準として、歩行スピード0.85m/sを報告しています。
なお、健常者は20代〜70代まで、およそ1.3m/sのスピードで歩くことが報告されています(Chui KK, 2010; Gomez Bernal A, 2016)。
健常者と同じスピードとまではいかずとも、ある程度のスピードがあれば『地域での制限のない移動が可能』とされており、歩行スピードが移動において重要であることが示されています。
ADL自立度が高い
歩行スピードが速い人ほど、ひとりで行える日常生活動作が多い傾向があります。
2022年の研究では、脳卒中患者さん536人を対象にし、歩行スピードとADL自立度との関係を調査しました。
結果として、歩行スピードが最も遅い場合(0.4m/s未満)のADL自立確率は40%だったものの、速い場合(0.8m/s超)は70%になったことが報告されました。
このことから、歩行スピードが速い人ほど、『ひとりで移動できる範囲が広い』『ひとりでできる日常生活動作が多い』と言えます。
メリット④ 生活の質(QOL)が高い

歩行スピードが速い人ほど、QOLが高い傾向があります。
QOL(Quality of Life:生活の質)とは?
QOLとは、心身の健康、生活の満足度、社会的つながりなどを含めた「人生の豊かさ」のことです。
2024年の研究では、発症から2週間以内の脳卒中患者さん1,475人を対象にし、歩行スピードとQOLとの関係を調査しました。
結果として、発症2週間時点での歩行スピードが速い人たちは、
- 3ヶ月後と12ヶ月後の移動、セルフケア(身の回りの動作)、日常生活の問題を抱えるリスクが低い
- 12ヶ月後の痛み/不快感の問題を抱えるリスクが低い
ことが明らかになりました。
このことから、急性期から速く歩ける人は、将来的に高いQOLレベルを獲得する可能性が高いと言えます。
慢性期でも同様の報告がなされています。
2019年の研究では、慢性期脳卒中患者さん25人を対象にし、歩行スピードの向上とQOLの向上との関係を調査しました。
この研究では12週間にわたってリハビリが行われました。
リハビリが終了した12週後、リハビリ開始前と比べると、歩行スピードとともにQOLが向上していました。
このことから、発症から時間が経った慢性期でも、歩行スピードの向上とともにQOLが向上する可能性があると言えます。
メリット⑤ 社会参加レベルが高い

歩行スピードが速い人ほど、社会参加レベルが高い傾向があります。
社会参加とは?
社会参加とは、働くことや趣味活動、地域の集まりへの参加など、家庭や施設の外で他者とかかわる活動全般を指します。
復職と関係がある
脳卒中を発症された方が社会復帰されるときに壁になるのが『復職』です。
2019年の報告によると、日本における脳卒中後の復職率は45%ほどであるとされています。
復職には色々なことが関わっており、脳卒中の後遺症が軽度であったとしても、職場の事情で復職が難しいケースもあります。
したがって、『こういう状態になれば必ず復職できる』というわけではないのですが、海外の研究では、歩行スピードが速い人は復職しやすい傾向があることが報告されています。
2019年の研究では、脳卒中患者さん46人と健常者15人を対象にし、歩行スピードと復職の関係を調査しました。
結果として、脳卒中患者さんは健常者よりも歩行スピードが遅いものの、0.93m/s以上の歩行スピードを有する場合、復職しやすくなることが明らかになりました。
歩行スピードが速い人は、通勤ラッシュ時など人混みの中でも周囲の人の歩行ペースに合わせて歩くことができる、というのが一因かもしれません。
社会参加レベルの高さと関係がある
社会参加の中で『仕事』は大きな要素のひとつですが、社会参加は仕事だけではありません。
歩行スピードが速い人は、仕事だけにとどまらず、その他の社会参加のレベルも高いことが明らかになっています。
2019年の研究では、慢性期脳卒中患者105人を対象にし、歩行スピードと社会参加レベルとの関係を調査しました。
なお、社会参加レベルは『LIFE-H 3.1』という質問票を使って調べています。
LIFE-H 3.1とは?
LIFE-H 3.1とは、日常生活や社会参加の達成度を評価するための質問票で、障害のある人の生活の質や自立度を多面的に把握するツールです。
結果として、歩行スピードが遅い人たちよりも速い人たちの方がLIFE-H 3.1のスコアが高い、つまり社会参加レベルが高いことが明らかになりました。
これらのことから、歩行スピードが速い人は『復職しやすい』『社会参加レベルが高い』と言えます。
なぜ歩行スピードが速いとこれらのメリットを得られるのか?

それは、『歩行スピードが速い=身体能力が高い』からです。
2025年の研究では、システマティックレビューという手法を用い、世界中の研究論文を集め、脳卒中患者さんの歩行スピードを予測する因子を報告しました。
システマティックレビューとは?
システマティックレビューとは、あるテーマについての複数の研究を体系的に集め、評価し、全体としての結論を導く方法です。
結果として、歩行スピードを予測する要因として以下のような身体機能が挙げられました。
- バランス能力
- 筋力
- 痙縮の程度
- 感覚障害の有無
つまり、歩行スピードが速い人というのは、これらの機能が高い(または障害が少ない)傾向にあるということです。
ここで重要なのは、『歩行スピードが速いから再発しにくくなる/復職しやすくなるなどのメリットを得られる』という因果関係ではないということです。
例えば復職において、会社から『あなたは速く歩けるから復職を許可します』と評価されるのではなく、身体能力が高いからこそ、結果として速く歩けていて、活動量も多く、できることも多いのです。
したがって、『歩行スピードが速い=脳卒中の再発リスクが低い・復職に有利』というのは、直接的な因果ではなく、背景にある身体能力の高さによるものだと捉えるのが自然です。
歩行スピードの速さは、あくまでも指標として捉えておくのが大事です。
まとめ
歩行スピードが速いことのメリットは次の5つです。
- 脳卒中発症(再発)のリスクが低い
- 歩きかたがよい
- 日常生活動作(ADL)の自立度が高い
- 生活の質(QOL)が高い
- 社会参加レベルが高い
歩行スピードは適切なリハビリを行うことで向上します。
歩行スピードを上げるためのリハビリについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
担当の理学療法士さんと相談しながら、歩行スピードの評価や、歩行スピードを向上させるリハビリに取り組まれてみてはいかがでしょうか。
また、BRAINでも歩行スピードを向上させるためのリハビリを提供できますので、ご興味がある方はよかったらお問い合わせくださいませ。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!
参考文献
Quan M, Xun P, Wang R, He K, Chen P. Walking pace and the risk of stroke: A meta-analysis of prospective cohort studies. J Sport Health Sci. 2020 Dec;9(6):521-529. doi: 10.1016/j.jshs.2019.09.005. Epub 2019 Sep 13. PMID: 33308803; PMCID: PMC7749229.
Zeki Al Hazzouri A, Mayeda ER, Elfassy T, Lee A, Odden MC, Thekkethala D, Wright CB, Glymour MM, Haan MN. Perceived Walking Speed, Measured Tandem Walk, Incident Stroke, and Mortality in Older Latino Adults: A Prospective Cohort Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017 May 1;72(5):676-682. doi: 10.1093/gerona/glw169. PMID: 27549992; PMCID: PMC5964741.
Li N, Zhang J, Du Y, Li J, Wang A, Zhao X. Gait speed after mild stroke/transient ischemic attack was associated with long-term adverse outcomes: A cohort study. Ann Clin Transl Neurol. 2024 Dec;11(12):3163-3174. doi: 10.1002/acn3.52222. Epub 2024 Oct 11. PMID: 39394716; PMCID: PMC11651184.
Jarvis HL, Nagy P, Reeves ND. A Faster Walking Speed Is Important for Improving Biomechanical Function and Walking Performance in Stroke Survivors. J Appl Biomech. 2025 Jan 10;41(1):70-86. doi: 10.1123/jab.2023-0230. Erratum in: J Appl Biomech. 2025 Jan 10;41(2):189. doi: 10.1123/jab.2025-0005. PMID: 39753123.
Quan M, Xun P, Wang R, He K, Chen P. Walking pace and the risk of stroke: A meta-analysis of prospective cohort studies. J Sport Health Sci. 2020 Dec;9(6):521-529. doi: 10.1016/j.jshs.2019.09.005. Epub 2019 Sep 13. PMID: 33308803; PMCID: PMC7749229.
An S, Lee Y, Shin H, Lee G. Gait velocity and walking distance to predict community walking after stroke. Nurs Health Sci. 2015 Dec;17(4):533-8.
Chui KK, Lusardi MM. Spatial and temporal parameters of self-selected and fast walking speeds in healthy community-living adults aged 72-98 years. J Geriatr Phys Ther. 2010;33(4):173-83.
Gomez Bernal A, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Losa-Iglesias ME. Reliability of the OptoGait portable photoelectric cell system for the quantification of spatial-temporal parameters of gait in young adults. Gait Posture. 2016;50:196-200.
Torres JL, Andrade FB, Lima-Costa MF, Nascimento LR. Walking speed and home adaptations are associated with independence after stroke: a population-based prevalence study. Cien Saude Colet. 2022 Jun;27(6):2153-2162. doi: 10.1590/1413-81232022276.13202021. Epub 2021 Aug 20. PMID: 35649005.
Zhao Y, Liao X, Gu H, Jiang Y, Jiang Y, Wang Y, Zhang Y. Gait speed at the acute phase predicted health-related quality of life at 3 and 12 months after stroke: a prospective cohort study. J Rehabil Med. 2024 Apr 15;56:jrm24102. doi: 10.2340/jrm.v56.24102. PMID: 38616713; PMCID: PMC11031874.
Grau-Pellicer M, Chamarro-Lusar A, Medina-Casanovas J, Serdà Ferrer BC. Walking speed as a predictor of community mobility and quality of life after stroke. Top Stroke Rehabil. 2019 Jul;26(5):349-358. doi: 10.1080/10749357.2019.1605751. Epub 2019 May 7. PMID: 31063439.
佐伯 覚, 蜂須 賀明子, 伊藤 英明, 加藤 徳明, 越智 光宏, 松嶋 康之, 脳卒中の復職の現状, 脳卒中, 論文ID 10668, 公開日 2019/08/08, Online ISSN 1883-1923, Print ISSN 0912-0726,
Jarvis HL, Brown SJ, Price M, Butterworth C, Groenevelt R, Jackson K, Walker L, Rees N, Clayton A, Reeves ND. Return to Employment After Stroke in Young Adults: How Important Is the Speed and Energy Cost of Walking? Stroke. 2019 Nov;50(11):3198-3204. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.025614. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31554503; PMCID: PMC6824505.
Faria-Fortini I, Polese JC, Faria CDCM, Teixeira-Salmela LF. Associations between walking speed and participation, according to walking status in individuals with chronic stroke. NeuroRehabilitation. 2019;45(3):341-348. doi: 10.3233/NRE-192805. PMID: 31796694.
Jasper AM, Lazaro RT, Mehta SP, Perry LA, Swanson K, Reedy K, Schmidt J. Predictors of gait speed post-stroke: A systematic review and meta-analysis. Gait Posture. 2025 Sep;121:70-77. doi: 10.1016/j.gaitpost.2025.04.029. Epub 2025 Apr 26. PMID: 40319767.











