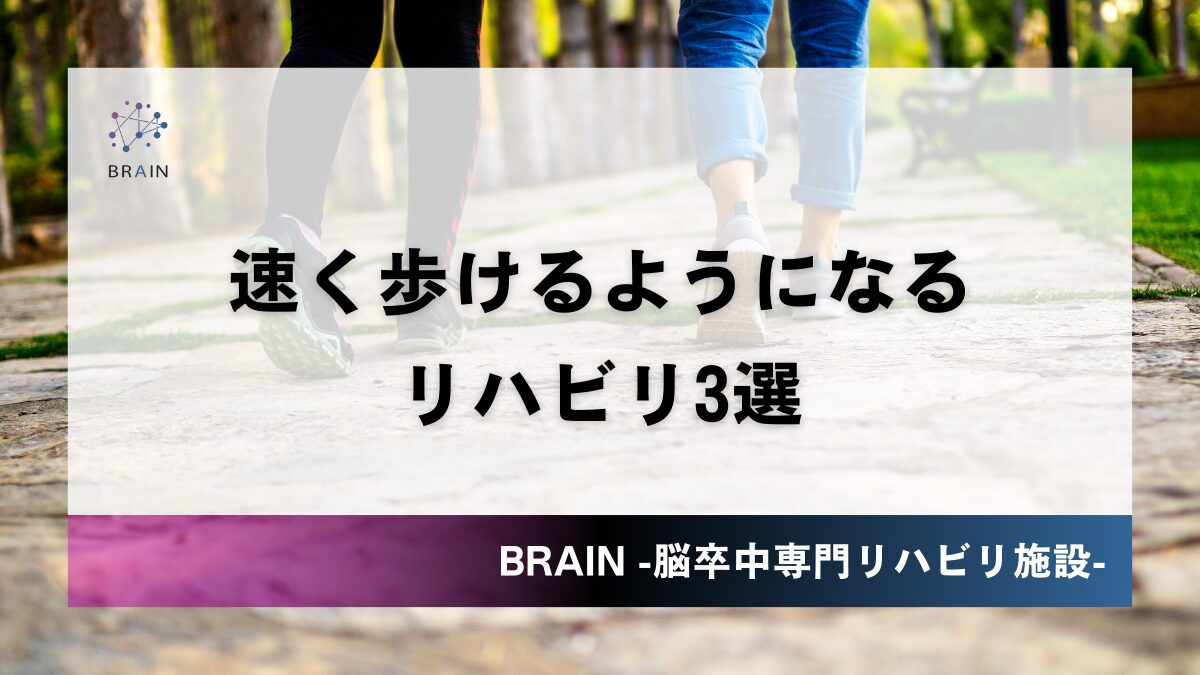
脳卒中を発症すると、歩行障害(ほこうしょうがい)が表れます。
歩行障害のひとつに『歩行スピードの低下』があります。
歩行スピードが速い人は次の5つのメリットが得られることが科学的に明らかになっています。
- 脳卒中発症(再発)のリスクが低い
- 歩きかたがよい
- 日常生活動作(ADL)の自立度が高い
- 生活の質(QOL)が高い
- 社会参加レベルが高い
歩行スピードがゆっくりな人も、リハビリをすることによって歩行スピードは上がります。
本記事では、歩行スピードを上げるために有効なリハビリを3つ紹介します。
情報の信頼性について
・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。
・本記事の情報は、主に信頼性の高いシステマティックレビュー研究から得られたデータを引用しています。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー
エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!
詳細はこちら
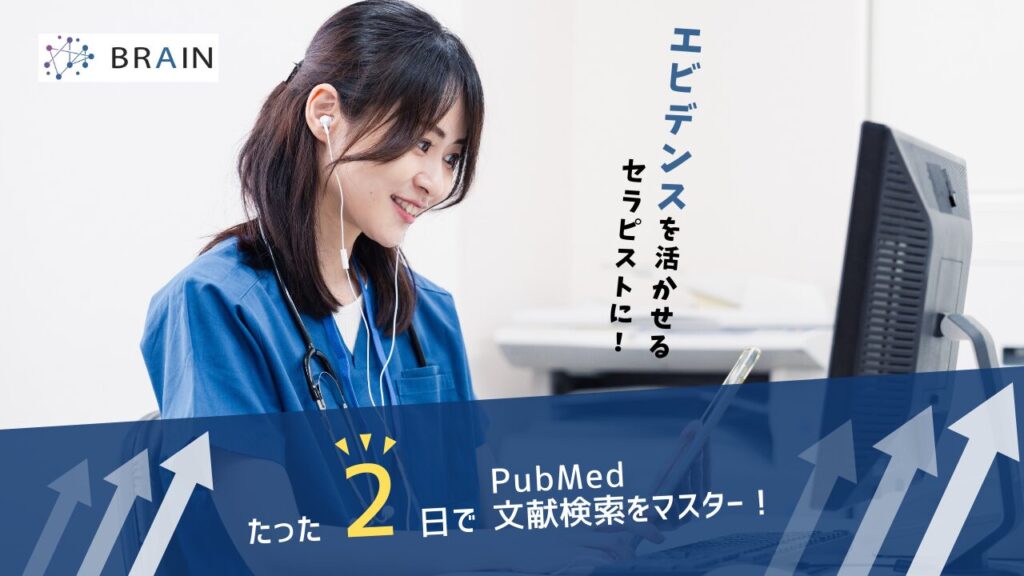
文献検索CAMP
PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。
詳細はこちら
脳卒中患者さんの歩行スピードを上げるリハビリ3選
歩行スピードを上げるために有効なリハビリは次の3つです。
- トレッドミルトレーニング
- 免荷式トレッドミルトレーニング
- 高強度トレーニング
以下、詳しく解説します。
リハビリ① トレッドミルトレーニング/免荷式トレッドミルトレーニング

トレッドミルトレーニングとは?
トレッドミルトレーニングは、トレッドミルマシンの上を歩くリハビリです。
マシン上で速度設定を行うことができるため、一定の速度・負荷で歩くことができるのが特長です。
トレッドミルトレーニングの効果
2017年の研究では、システマティックレビューという手法を用い、世界中の研究論文を集め、トレッドミルトレーニングの歩行スピードへの効果を調査しました。
889人分のデータを分析した結果、『トレッドミルトレーニングは他のリハビリを行う場合と比べ、歩行速度を向上させるのに有効である』と示されました。
ただし、同研究の別の分析結果によると、トレッドミルトレーニングを活用するには条件があることが明らかになりました。
- 歩行スピードを向上させるためには週1〜2回行うだけでは有効と言えず、週3回以上行う必要がある
- 歩行見守りレベル以上の患者さんには有効だが、軽介助〜重度介助の患者さんには有効とは言えない
したがって、適正を見極めながらトレッドミルトレーニングを活用する必要があると言えます。
リハビリ② 免荷式トレッドミルトレーニング
免荷式トレッドミルトレーニングとは?
トレッドミルトレーニングに免荷装置を付け加えたものを免荷式トレッドミルトレーニングといいます。
身体を吊り上げることによって、体重を軽くして歩く練習を行うことができます。
免荷式トレッドミルトレーニングの効果
上述の2017年の研究で、免荷式トレッドミルトレーニングの効果も検証されています。
672人分のデータを分析した結果、『免荷式トレッドミルトレーニングは他のリハビリを行う場合と比べ、歩行速度を向上させるのに有効である』と示されました。
ただし、トレッドミルトレーニングと同様に、以下の条件を守る必要があります。
- 歩行スピードを向上させるためには週1〜2回行うだけでは有効と言えず、週3回以上行う必要がある
- 歩行見守りレベル以上の患者さんには有効だが、軽介助〜重度介助の患者さんには有効とは言えない
免荷式トレッドミルトレーニングも、適性を見極めながら行うのが望ましいと言えるでしょう。
リハビリ③ 高強度トレーニング

高強度トレーニングとは?
高強度トレーニングとは、筋力や持久力を高めるために、心拍数や筋への負荷が高い状態で行う運動のことです。
2019年の研究では、高強度トレーニングの定義として、以下のいずれかに該当するものを指す、とされています。
- 60〜84% HRR/Vo2peak
- 70〜89% HRmax
- 14〜16 Borg RPE
医学的には「心拍数が最大の70〜85%になるくらい」「運動のキツさを0〜20で評価したときに14〜16くらい(ややきつい〜きつい)」とされていますが、ざっくり言えば「ちょっと頑張らないといけない」と感じる程度の運動です。
トレッドミルトレーニングのスピードを速くし、速く歩かなければならない状況にすることで、高強度トレーニングを行うことができます。
高強度トレーニングの効果
上述の2019年の研究では、脳卒中患者さんの歩行スピードを上げるにあたり、高強度トレーニングと低強度トレーニングの効果を検証しました。
345人分のデータを分析した結果、『高強度トレーニングは、低強度トレーニングよりも歩行スピードの向上に有効である』ことが明らかになりました。
上述のようにトレッドミルトレーニングには歩行スピードを速くする効果がありますが、高強度にすることによってその効果をさらに高めることができるということです。
少しキツい運動になりますが、耐えられる方は高強度トレーニングにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
高強度トレーニングの安全性
『キツい運動は心臓や血管に負担がかかるし、転ぶかもしれないし、怖い』と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、高強度トレーニングは特別にリスクが高いわけではないことが報告されています。
上述の2019年の研究では、高強度トレーニングと低強度トレーニングとで、有害事象の発生に違いがあるかどうかを調べました。
有害事象とは?
有害事象とは、医療やリハビリなどの介入後に起こる、望ましくない症状や変化のことを指します。怪我や痛みの発生、病気の発生などを指します。ただし、必ずしも治療との因果関係があるとは限りません。
56〜210人分のデータを分析した結果、『高強度トレーニングは、低強度トレーニングと比べて、有害事象が多いとは言えない(リスクに差はない)』ことが明らかになりました。
つまり、高強度トレーニングを行うからといって特別にリスクが高くなるわけではないということです。
なぜ有酸素運動が有効なのか?
それは『心肺機能を高めることが歩行スピードを速くすることに寄与するから』です。
脳卒中患者さんは、健康な人と比べて歩くスピードが遅い傾向にあります。
これは、『筋力が落ちたから遅い』という理由だけでなく、身体のエネルギーの使いかたや負荷の感じかたが変わってしまっていることが関係しています。
2021年の研究では、脳卒中患者40名と健常者15名を対象にし、トレッドミルでさまざまなスピード(普段の70〜130%)で歩いてもらい、呼吸に含まれる酸素の量から「どれくらい体に負担がかかっているか」「どれくらいエネルギーを使っているか」を調査しました。
結果として、次のことがわかりました。
- 脳卒中患者さんは、健常者に比べて歩くスピードが遅い
- しかも、同じように歩いていても、脳卒中の方のほうが体にかかる負荷は大きく、エネルギーの消費効率(燃費)も悪い
- スピードを上げると、エネルギーの効率(燃費)はよくなるが、今度は体にかかる負荷が大きくなりすぎて、長く歩けなくなってしまう
つまり、脳卒中患者さんは『もっと速く歩いたほうが燃費はいい』と無意識でわかっていても、身体にとって“オーバーワーク”になってしまうため、自分にとって無理のない“ゆっくりしたスピード”を自然に選んでいる、ということです。
たとえるなら、エンジンの小さな車で坂道を登っているような状態です。
スピードを出せば効率は良くても、エンジンが焼けついてしまうかもしれない。だからこそ、安全で長く動けるスピードを選ぶのです。
ここでいうエンジンとは、心臓や肺などの「心肺機能」のことを指しています。
脳卒中患者さんは、有酸素運動を行い、心肺機能が向上すれば、エンジンが大きくなり、余裕を持って速いスピードで歩けるようになる可能性があるということです。
まとめ
本記事のまとめです。
- 歩行スピードを上げるのに有効なリハビリは①トレッドミルトレーニング②免荷式トレッドミルトレーニング③高強度トレーニング
- 有酸素運動を行うことで心肺機能が向上し、余裕をもって歩行スピードを上げられるようになる
よかったら、担当の理学療法士さんと相談しながら、歩行スピードを上げるリハビリを検討されてみてください。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!
参考文献
Mehrholz J, Thomas S, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 17;8
Luo L, Zhu S, Shi L, Wang P, Li M, Yuan S. High Intensity Exercise for Walking Competency in Individuals with Stroke: A Systematic Review and Meta Analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Dec;28(12):104414.
Blokland I, Gravesteijn A, Busse M, Groot F, van Bennekom C, van Dieen J, de Koning J, Houdijk H. The relationship between relative aerobic load, energy cost, and speed of walking in individuals post-stroke. Gait Posture. 2021 Sep;89:193-199. doi: 10.1016/j.gaitpost.2021.07.012. Epub 2021 Jul 21. PMID: 34332288.











