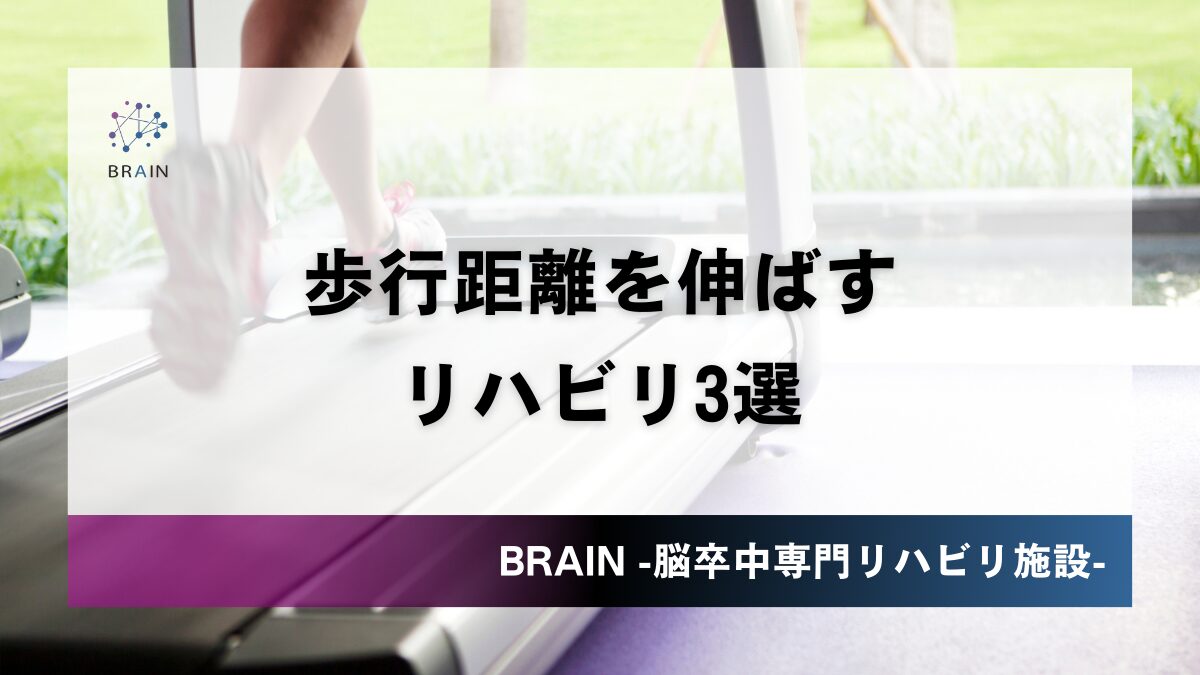
脳卒中を発症すると、歩行障害(ほこうしょうがい)が表れます。
そのひとつが「歩行距離の短縮」です。
これは、連続して長く歩けなくなってしまう状態を指します。
歩行距離が長い、つまり「長く歩ける」ことには4つの大きなメリットがあります。
リハビリによって、歩行距離は伸ばすことが可能です。
本記事では、歩行距離を伸ばすために有効なリハビリ方法を3つご紹介します。
情報の信頼性について
・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。
・本記事の情報は、信頼性の高いシステマティックレビュー研究から得られたデータや、観察研究を引用しています。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー
エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!
詳細はこちら
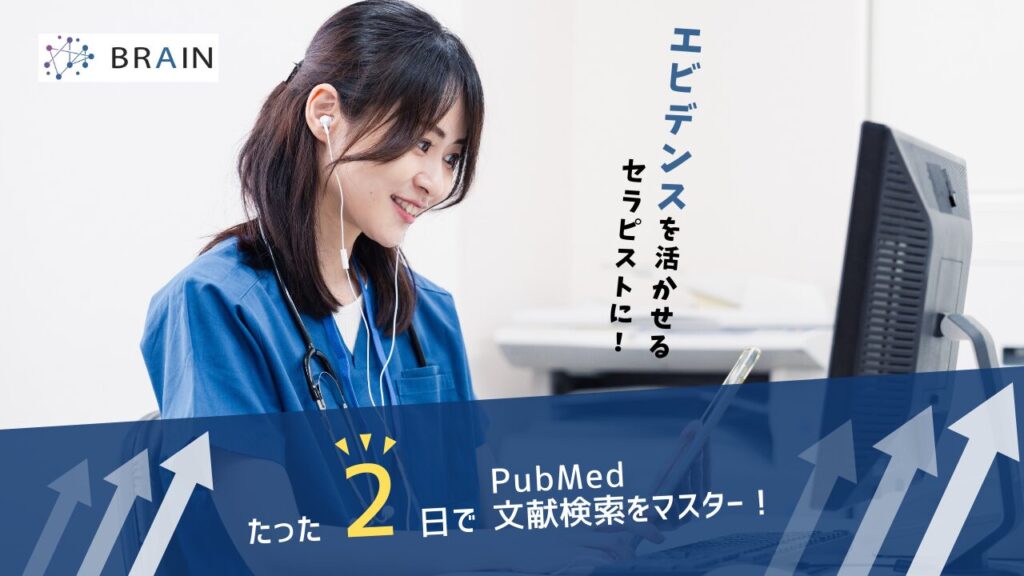
文献検索CAMP
PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。
詳細はこちら
歩行距離を伸ばすリハビリ3選
歩行距離を伸ばすのに有効なリハビリは次の3つです。
- トレッドミルトレーニング
- 高強度トレーニング
- 課題指向型訓練
以下、詳しく説明します。
リハビリ① トレッドミルトレーニング

トレッドミルトレーニングとは?
トレッドミルトレーニングは、トレッドミルマシンの上を歩くリハビリです。
速度を設定できるため、一定の速度や負荷で歩行練習ができるのが特長です。
このトレーニングに免荷装置(身体を吊り上げる装置)を組み合わせたものは「免荷式トレッドミルトレーニング」と呼ばれます。
免荷によって体重を軽くし、負担を減らして歩く練習が可能です。
本記事では、免荷なし・免荷ありの両方を「トレッドミルトレーニング」として説明します。
トレッドミルトレーニングの効果
2017年の研究では、システマティックレビューという手法を用い、世界中の研究論文を集め、トレッドミルトレーニングの歩行距離への効果を調査しました。
1041人分のデータを分析した結果、『トレッドミルトレーニングは他のリハビリを行う場合と比べ、歩行距離を向上させるのに有効である』と示されました。
ただし、同研究の別の分析結果によると、トレッドミルトレーニングを活用するには条件があることが明らかになりました。
- 歩行距離を向上させるためには週5回以上行う必要があり、週5回未満では有効とは言えない
- 歩行見守りレベル以上の患者さんには有効だが、軽介助〜重度介助の患者さんには有効とは言えない
したがって、適正を見極めながらトレッドミルトレーニングを活用する必要があると言えます。
さらに、2021年のシステマティックレビューhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33744188/では、トレッドミルトレーニングと平地歩行練習(病院の廊下、公園、道路などでの歩行)を比較しました。
おそらく本記事をご覧になっている脳卒中当事者の方も、平地歩行練習をリハビリで一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
この研究では、どちらがより歩行距離の向上に効果的かを検証し、その結果、トレッドミルトレーニングの方が有効であることが報告されています。
以上から、トレッドミルマシンが利用できる環境であれば、積極的に取り入れる価値があるといえます。
リハビリ② 高強度トレーニング

高強度トレーニングとは?
高強度トレーニングとは、筋力や持久力を高めるために、心拍数や筋への負荷が高い状態で行う運動のことです。
2019年の研究では、高強度トレーニングの定義として、以下のいずれかに該当するものを指す、とされています。
- 60〜84% HRR/Vo2peak
- 70〜89% HRmax
- 14〜16 Borg RPE
医学的には「心拍数が最大の70〜85%になるくらい」「運動のキツさを0〜20で評価したときに14〜16くらい(ややきつい〜きつい)」とされていますが、ざっくり言えば「ちょっと頑張らないといけない」と感じる程度の運動です。
トレッドミルトレーニングのスピードを速くし、速く歩かなければならない状況にすることで、高強度トレーニングを行うことができます。
高強度トレーニングの効果
上述の2019年の研究では、脳卒中患者さんの歩行距離を上げるにあたり、高強度トレーニングと低強度トレーニングの効果を検証しました。
777人分のデータを分析した結果、『高強度トレーニングは、低強度トレーニングよりも歩行距離の向上に有効である』ことが明らかになりました。
上述のようにトレッドミルトレーニングには歩行距離を伸ばす効果がありますが、高強度にすることによってその効果をさらに高めることができるということです。
少しキツい運動になりますが、耐えられる方は高強度トレーニングにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
リハビリ③ 課題指向型訓練

課題指向型訓練とは?
課題指向型訓練とは、何らかの運動課題を通して身体機能を向上させるリハビリです。
例えば、次のような練習があります。
- ステップ練習(立ったまま足を前に出す)
- 段差練習(足を20cmの台に乗せる)
- ボール練習(足の下にボールを置き、転がす)
これらの課題では、足の動きやバランスを使うため、リハビリとしての効果が期待できます。
課題指向型訓練は、脳卒中リハビリにおいて広く効果が認められている方法です。
課題指向型訓練について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
課題指向型訓練の効果
2016年の研究では、システマティックレビューという手法を用い、システマティックレビューという手法を用いて、課題指向型訓練が脳卒中患者さんの歩行距離向上に有効かどうかを調査しました。
その結果、課題指向型訓練は、リハビリを行わない場合や普段通りの生活を送る場合と比べて、歩行距離を伸ばす効果があることが報告されました。
このことから、課題指向型訓練は歩行距離の向上に有効なリハビリ方法の一つといえます。
課題指向型訓練を成功させるためのポイント
課題指向型訓練では、「どのような運動課題を行うか」が成果を左右する重要なポイントです。
単にステップ練習や段差練習を行えば長く歩けるようになる、というわけではありません。
2025年の研究では、脳卒中患者さん68人を対象にし、歩きかたと歩行距離(持久力)の関係を調査しました。その結果、次の2つの動作が関係していることが明らかになりました。
- 踵を接地するときの足と地面の角度
- 足を前方に振り出す直前の足と地面の角度
つまり、「踵からしっかり接地する」や「足を振り出す際に踵を浮かせてから前に出す」といった動作が、歩行距離を伸ばすポイントになるということです。
課題指向型訓練では、こうした要素を踏まえてリハビリを行います。
例えば、単にステップ練習を繰り返すのではなく、「踵からつくことを意識して足を前に出す」「つま先で地面を押すように蹴り出す」など、動作の質を意識する工夫が必要になります。
まとめ
歩行距離を伸ばすのに有効なリハビリは次の3つです。
- トレッドミルトレーニング
- 高強度トレーニング
- 課題指向型訓練
“長く歩ける” ことには4つの大きなメリットがあります。
担当の理学療法士さんと相談しながら、歩行距離を伸ばすリハビリをすべきかどうか、検討されてみてはいかがでしょうか。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!
参考文献
Mehrholz J, Thomas S, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 17;8
Nascimento LR, Boening A, Galli A, Polese JC, Ada L. Treadmill walking improves walking speed and distance in ambulatory people after stroke and is not inferior to overground walking: a systematic review. J Physiother. 2021 Apr;67(2):95-104.
Luo L, Zhu S, Shi L, Wang P, Li M, Yuan S. High Intensity Exercise for Walking Competency in Individuals with Stroke: A Systematic Review and Meta Analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Dec;28(12):104414.
French B, Thomas LH, Coupe J, McMahon NE, Connell L, Harrison J, Sutton CJ, Tishkovskaya S, Watkins CL. Repetitive task training for improving functional ability after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 14;11(11):CD006073.











