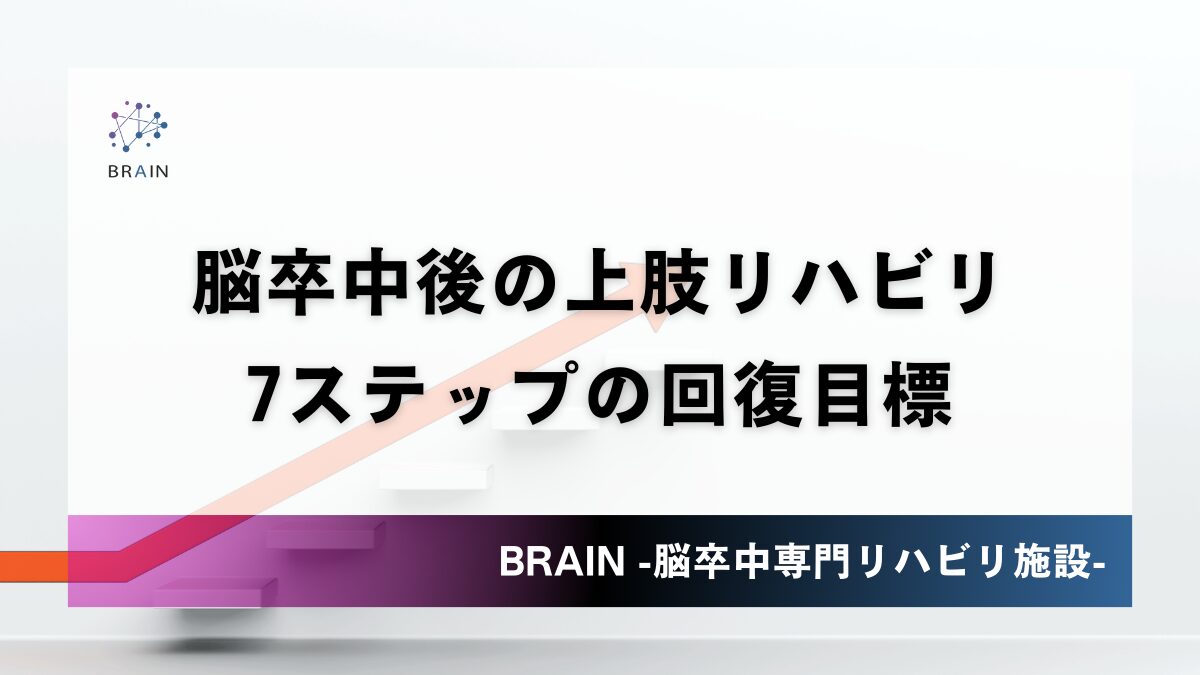
脳卒中のあと、手や腕が思うように動かないと、とても不安になりますよね。
- 「自分の手はどこまで回復できるんだろう…?」
- 「今の段階で、何を目指せばいいのか分からない…」
そんな悩みを抱えている方やご家族は少なくありません。
私たちBRAINでは、脳卒中後の上肢リハビリの回復の目標を7つのステップに分けて考えるようにしています。
ステップごとに「今できること」と「次に目指すこと」が整理されるので、ご自身の状況に照らし合わせやすくなります。
本記事は、その7つのステップを順番にご紹介していきます。
きっと、今のあなたのリハビリを考えるヒントになるはずです。
情報の信頼性について
・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。
・本記事の情報は、信頼性の高い観察研究から得られたデータを引用しています。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー
エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!
詳細はこちら
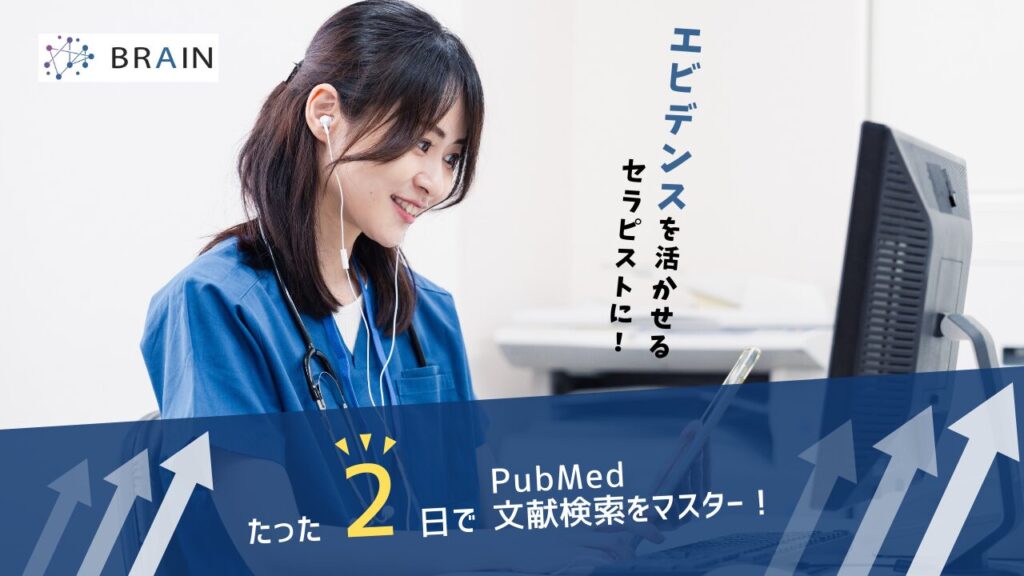
文献検索CAMP
PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。
詳細はこちら
なぜ重症度ごとに目標を分けるのか
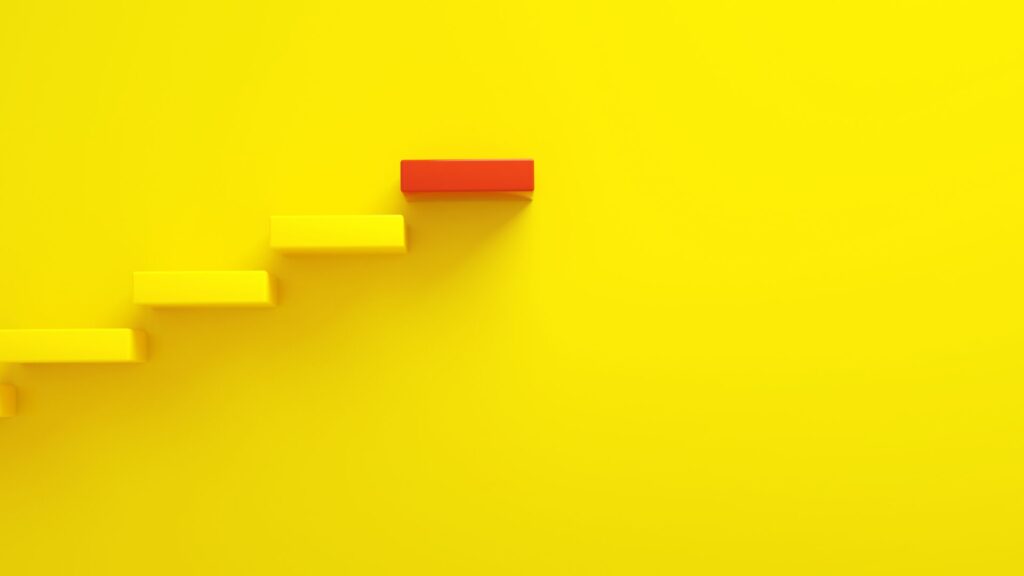
脳卒中のあとリハビリをされている患者さんやご家族の多くは、やはり「発症前のように手を自由に動かせるようになりたい」と願っていると思います。
もちろん、その気持ちは私たちセラピストも理解していますし、最終的にそこを目指して一緒に歩んでいることに変わりはありません。
ただし、そこに至るまでの道のりは一足飛びではありません。
例えば、手がまったく動かない状態から、3日後にいきなりスマホを操作できるようになることは現実的には難しいことが多いです。
一方で、手が動かない状態でも「少しでも動くようになること」や「自主トレーニングで手を動かせるようになること」であれば、十分に達成可能です。
そしてその小さな前進が積み重なることで、麻痺した手を生活の中で使う機会が増え、それ自体がリハビリとなり、さらに次の回復へとつながっていきます。
だからこそ、重症度に応じて「現実的に達成できる目標」を設定し、ひとつひとつドアを開けるようにステップを進めていくことが大切なのです。
魔法のように一瞬で元に戻るわけではありませんが、その積み重ねが確かな回復への道になります。
つまり、「なぜ重症度ごとに目標を分けるのか」と言えば、それは“今の状態に合った、達成可能で意味のあるステップを積み重ねることが、最終的な回復につながるから”なのです。
重症度分類におけるFMAUE

これから紹介する「重症度ごとのリハビリ目標」は、FMAUE(フーグル・マイヤー上肢機能評価)という検査をもとにしています。
FMAUEは、脳卒中後の手や腕の回復を評価するために世界中で使われているテストで、0点から66点までの合計点で評価します。
- 点数が低ければ、まだ動かすことが難しい段階
- 点数が高ければ、より細かい動作までできる段階
という目安になります。
FMAUEは日本でも広く使われている評価スケールです。
リハビリの現場でも日常的に行われているため、すでに評価を受けていて、ご自身の点数をご存じの方も多いと思います。
もし覚えていなければ、リハビリ実施計画書や経過報告書などを見直してみると、点数が記載されているかもしれません。
今回はFMAUEという評価に基づいて「ステップ1〜7」と分けてご説明します。
注意点として、ここでご紹介するステップは公式に定められたものではありません。
私たちBRAINが、これまでの臨床経験や研究のエビデンスをもとに独自に分類したものです。
あらかじめその点をご理解いただけますと幸いです。
点数とステップを照らし合わせていただければ、ご自身の状態に近いところが分かると思います。
FMAUEに基づく7ステップの回復目標

ステップ1(FMAUE 0〜9点:はじめのステップ)
この段階は、手や腕を自分の力でまったく動かせない状態を指しています。
リハビリの目標は、「リハビリ中であれば肩や腕を動かせる状態に持っていくこと」です。
つまり、まずはセラピストとのマンツーマンの練習の中で、動きを出現させることが大切です。
その一歩が、次の回復につながる基盤となります。
ステップ2(FMAUE 10〜22点:少し動き始めるステップ)
この段階は、リハビリ中であれば肩や腕を少し動かせる状態を指します。
目標は大きく分けて二つあります。
ひとつ目の目標は、「セラピストの手を借りずに、自主トレーニングでも動かせるようになること」です。
最初はマンツーマンでしか動かせなかった腕を、だんだんとセラピストが触れず見守るだけでもご自身で動かせるようにしていきます。
こうして自主トレでも腕を動かせるようになると、1日の中で手を使う時間が大きく増えます。
マンツーマンのリハビリを1時間、自主トレーニングを2時間、とすると、腕を1日3時間使うことになり、運動量が増えることで回復につながります。
二つ目の目標は、「座った状態で腕を肩の高さまで上げられるようになること」です。
これは次のステップにつながる大切な基準で、生活の中で麻痺手を活用するための準備段階となります。
つまり、この段階では、
- 自主トレで腕を動かせるようになること
- 座位で肩の高さまで上げられるようになること
この2つを並行して目指すことが大切です。
ステップ3(FMAUE 23〜35点:生活で手を使い始めるステップ)
この段階は、腕を肩の高さくらいまで上げられる状態を指します。
目標は、「補助具を活用して、生活の中で麻痺手を使えるようになること」です。
マンツーマンリハビリや自主トレーニングを積み重ねて、このレベルに到達すると、上肢装具を活用しながら生活動作の中で手を使えるようになっていきます。
特に近年注目されているのが、電気刺激付き装具です。
これは、腕の筋肉に電気を流すことで、手を「握る」「開く」といった動作をサポートしてくれる装具です。
もし指がまったく動かせなくても、
- 腕は自分の力で上げる
- 指は装具の力で開閉する
という組み合わせが可能になります。
例えば、ブロックをつかんで移動させたり、軽い物を扱ったりと、実際に「物を操作する」ことができるようになるのです。
これにより、「麻痺手を生活の中で使う」ことが現実味を帯び、手を使う時間が一気に増えていきます。
マンツーマン1時間、自主トレ2時間、さらに生活場面で2時間。
合わせて1日5時間使えるようになれば、手を動かす総量は大幅に増加し、さらなる回復へとつながります。
ステップ4(FMAUE 36〜45点:支える・つかむステップ)
この段階は、補助具(上肢装具や生活便利グッズなど)を使えば、生活の中で麻痺手を活用できる状態を指します。
目標は、
- 「物を押さえる動作」を日常生活で使えるようにすること
- 上肢装具を外して「手を伸ばして物品をつかむ動作」を獲得すること
の2つです。
この段階に到達していれば、補助具を使うことで生活の中で麻痺手を使う力はすでに獲得できているはずです。
今後はリハビリを通して、段階的に装具の使用を減らし、最終的に装具なしで生活の中で使える動作を増やしていきます。
この段階において、装具なしで可能な代表的な動作は次の2つです。
- ものを押さえる:たとえば、健側の手で文字を書くときに、麻痺手で紙を押さえる動作。
- 物品に手を伸ばして掴む:手のひら全体でコップやブロックなどを大まかにつかんで離す動作。
なお、「物をつかむ」動作には大きく分けて「手握り」と「指握り」があります。
専門的には「Whole Hand Grasp」と「Digital Grasp」といいます。
この段階で目指すのは「手握り」で、まだ指を使った繊細な握り方までは求めません。
まずは大まかでいいので、装具なしで物をつかめることを目標にしましょう。
ステップ5(FMAUE 45〜54点:指先を使うステップ)
この段階は、上肢装具を使わなくても日用品を持ったり離したりできる状態を指します。
目標は、
- 「指握り(Digital Grasp)」の獲得
- 日常生活の中で麻痺手を使ったさまざまな物品操作を行えるようにすること
の2つです。
「指握り」とは、指先を使って小さな物をつまんだり、細かい操作をする持ち方のことです。
- ビー玉を持つ
- コインを持つ
- お箸を持ち上げる
といった、指先の動きを必要とする作業が可能になります。
指握りが獲得できれば、扱える物品の種類や数が一気に増え、日常生活の中で麻痺手を使える場面が格段に広がり、次のステップにつながります。
FMAUE 43〜45点が「生活で麻痺手を使えるようになりやすい」ライン
世界中で「脳卒中患者さんが麻痺手を生活の中で使えるようになるFMAUEスコアはどれくらいか?」ということが調べられています。複数の研究で、FMAUE43〜45点くらいが、そのラインであることが報告されています(Chin LF 2020; Hirayama K 2023)。
ステップ6(FMAUE 54〜65点:細かい動作を広げるステップ)
この段階では、麻痺手を日常生活でかなり使えるようになっています。
代表的な動作として、机の上のコップをつかみ、水を飲むといった動作ができるようになっているはずです。
目標は、
- 「細かい動作の獲得」
- 「できるレベル」と「しているレベル」のズレを解消すること
の2つです。
まず、「指握り」ができるようになったら、それを生活に応用していきましょう。
例えば、
- ボタンをとめたり外したりする
- コインを財布から出し入れする
- ペンを持って文字を書く
といった細かい動作を新たに獲得していきます。
一方で、この段階で問題になりやすいのが、「できるレベル」と「しているレベル」のズレです。
これは、「麻痺手を動かす力はあるのに、生活の中で実際にはあまり使っていない」状態を指します。
正直なところ、この段階に到達しても麻痺手は病前のようにスムーズではなく、重たさや固さ、思うようにいかない感覚が残ります。
そのため、つい非麻痺手ばかりを使ってしまい、麻痺手は使われなくなりがちです。
すると麻痺手の運動量が減り、せっかくの回復のチャンスが遠のいてしまいます。
少し大変に感じるかもしれませんが、麻痺手が持っている能力は生活の中でフル活用することが大切です。
なお、この「ズレ」には患者さんのやる気や気持ちだけでなく、さまざまな要因が関わります。
ご自身だけで抱え込まず、担当セラピストに評価してもらいながら、生活での使い方を一緒に工夫していきましょう。
ステップ7(FMAUE 66点:自然に使えるステップ)
この段階は、検査上は満点を取れていても、実際にはまだ動かしづらさが残っている状態を指します。
目標は、「病前のように自然に手を使えるようになること」です。
前の段階で細かい動作を獲得し、また「できるレベル」と「しているレベル」の乖離を解消して、日常的に手を使えるようになっていても、非麻痺側と比べるとまだ違和感が残ることは少なくありません。
例えば、手の重さや硬さを感じたり、思った通りの速さやスムーズさで動かせなかったりすることがあります。
その原因としては、筋肉の硬さや、筋肉が働くタイミングのずれなどが考えられます。
リハビリでは、こうした要因を少しずつ改善していき、最終的には病前のように自然に手を使える状態を目指していきます。
まとめ
今回は、脳卒中後の上肢リハビリについて、各ステップごとに異なるリハビリ目標を7つの段階に分けて解説しました。
実は、各ステップにおいて適切なリハビリ方法が存在します。
「どのステップにも有効な方法」はなく、ご自身のステップに合わせて、適切なリハビリ方法は変わります。
担当セラピストさんと、目標やリハビリ方法について相談してみてください。
特に、重度片麻痺に対して有効なリハビリをこちらの記事にまとめていますので、よかったらご覧ください。
どの段階にも目標があり、それぞれが次の回復につながるステップとなります。
脳卒中後のリハビリは、一気にゴールへたどり着くものではありません。
今日できること、明日できることを少しずつ増やしていく、その積み重ねが大きな回復につながります。
たとえ今は小さな変化に見えても、それは確実に次のステップへの扉を開いています。
「今の自分にできること」を大切にしながら、一歩一歩進んでいきましょう。
リハビリの無料体験を実施中!
といった方から選ばれています!
参考文献
Chin LF, Hayward KS, Brauer S. Upper limb use differs among people with varied upper limb impairment levels early post-stroke: a single-site, cross- sectional, observational study. Top Stroke Rehabil. 2020 Apr;27(3):224-235
Hirayama K, Matsuda M, Teruya M, Fuchigami T, Morioka S. Trends in amount of use to upper limb function in patients with subacute stroke: a cross-sectional study using segmental regression analysis. BMC Neurol. 2023 Dec 4;23(1):429.











